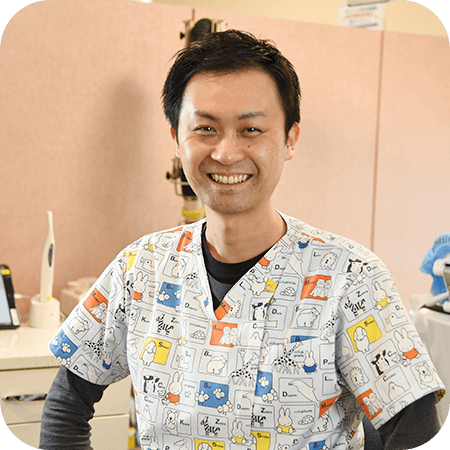赤ちゃんが食事を自分の手でつかんで食べる「手づかみ食べ」。その姿はほほえましいものですが、実はこの行動には発達や健康の面で多くのメリットがあることをご存じでしょうか。
今回は、手づかみ食べは「いつからいつまで」行うのが理想か、そしてその習慣がもたらす具体的な効果について、歯科医師の視点から詳しく解説します。
お子さんの健やかな成長を支えるためにも、離乳期の食べ方にはぜひ注目していただきたいポイントがあります。
目次
■赤ちゃんの手づかみ食べはいつからいつまで?
◎手づかみ食べ、いつから?
手づかみ食べは、一般的に生後8~9ヵ月頃からといわれています。この時期には親指と人差し指で物をつまむ動きが少しずつ可能になり、脳と手指の協調運動が発達してくるため、目で見たものを意図的につかんで口へ運ぶという一連の動作ができるようになります。
初めのうちは、柔らかく握りやすい大きさ・形状の食材(蒸した野菜スティックややわらかいおにぎりなど)を用いることで、安全にかつ意欲的に手づかみ食べへと導くことができます。
赤ちゃんにとってこの経験は、「自分で食べる・食べられた」という意思の育成につながり、自分でできるという自信(自己効力感)の発達を促します。
◎手づかみ食べ、いつまで?
生後12ヵ月頃を過ぎると、スプーンやフォークといった道具への関心が高まり始め、1歳半頃にはそれらの使用を試みるようになります。ただし、この段階で「道具の使用」へ急激に移行させるのではなく、手づかみと道具の併用期として捉えることが重要です。
なぜなら、まだ手指の器用さや、手と目の協応動作が完全には成熟していないため、無理に道具のみを使わせると、食べたいという気持ちが減退してしまう恐れがあります。
2歳頃になると、道具を用いた食事動作が徐々に安定してきます。この時期を目安に、手づかみから道具中心の食べ方へと自然に移行していくのが理想的です。ただし、発達の進み方には個人差があるため、他の子と比較する必要はありません。
むしろ、お子さん一人ひとりの発達段階を見極め、本人の興味と能力に応じて柔軟に対応することが重要です。
また、歯科的な視点から見ると、離乳食後期における手づかみ食べはよく噛むための筋肉(咀嚼筋)の発達を促し、顎の骨や口腔周囲筋の健全な成長を助けます。これにより、将来的に歯並びが自然になったり、発音の明瞭さにも好影響が期待できます。
以上のことから、「手づかみ食べはいつから?」の目安は生後8ヵ月頃、「いつまで?」は2歳前後を基準とし、個々の発達に応じて無理なく段階的に進めることが推奨されます。保護者の方はお子さんの行動をよく観察しながら、焦らず、楽しみながらこの貴重な成長過程を支えてあげてください。
■赤ちゃんの手づかみ食べのメリット
赤ちゃんの手づかみ食べには、以下に挙げるメリットがあります。
1.口周りや顎の発達を促す
手づかみ食べでは、咀嚼が必要な食材を自分の手で選び、自分のペースで食べるようになります。この行為により、口周りの筋肉や顎の発達が促され、歯並びや発音、将来の噛み合わせにも良い影響を及ぼすと考えられています。
やわらかすぎる離乳食ばかりでは育ちにくい「噛む力」を自然に育むためにも、手づかみ食べは重要です。
2.指先の発達を促進する
小さな食材を指でつまむ、手で握って口に運ぶといった動作を通じて、赤ちゃんの手先の器用さが養われます。こうした微細運動は、その後のスプーンやフォークの使用、歯みがき習慣、さらには絵を描く・字を書くといった日常動作にもつながっていく重要な基礎になります。
3.食べ物への興味や好奇心が育つ
食事に自分の手で関わることで、「これは何だろう?」という好奇心や、「これを食べてみたい」という意欲が育ちます。五感を使って食材に触れ、においや感触を体験することで、食べ物への理解が深まり、好き嫌いの軽減にもつながる可能性があります。
4.自立心が育つ
自分の意志で食べたいものを選び、手で食べる経験は、赤ちゃんにとって「自分でできた!」という達成感につながります。これは自立心の芽生えにもつながり、子どもが食事に前向きになる大きなきっかけとなることもあります。
5.食事のペースを自分で調整できる
スプーンで食べさせると、大人のペースに合わせがちになってしまい、赤ちゃんの満腹感・空腹感を無視してしまうことも。しかし、手づかみ食べでは赤ちゃん自身が「食べたいときに食べる」というペースを自然に覚えていきます。
このような経験から、満腹感や空腹感といった身体の感覚を自分で認識する力を養うことができ、幼い頃からこうしか感覚を身につけることで、将来的に過食を防ぎ、生活習慣病予防にもつながると考えられます。
6.口腔機能発達のサポートになる
噛む・舌を動かす・唇を閉じるなど、口腔機能は手づかみ食べを通じてバランスよく刺激されます。これにより、口がポカンと開きやすい、発音が不明瞭といったトラブルの予防にもつながります。
また、適切な時期に手づかみ食べを取り入れ、お口の機能や顎の骨が正常に発達することで歯並びが整い、将来的に矯正のリスクを減らせる可能性もあります。
7.食べこぼしを通して環境への学習ができる
手づかみ食べは食べこぼしも多くなりますが、それもまた学びの一環です。どの程度力を入れると潰れてしまうか、落ちるとどうなるか、などを通じて、食事中のルールや衛生意識も少しずつ身につけていきます。
保護者の方にとっては少し手間かもしれませんが、長期的にはとても有意義な経験になるでしょう。
■まとめ
赤ちゃんの手づかみ食べは、単なる「食べ方」ではなく、身体や心の発達を支える大切なステップです。
いつからいつまで行うかを見極めながら、成長段階に応じて適切なサポートを行うことで、お子さんの顎や歯並び、さらには生活習慣までに好影響を与える可能性があります。
五泉市駅前の浅井歯科医院では、歯科医師としての視点から、食育や口腔発達についても丁寧にアドバイスを行っています。気になることがあればお気軽にご相談ください。