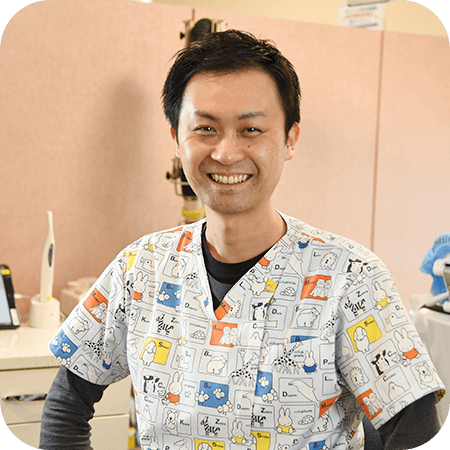過去のコラムでは、子どもの顎を鍛える上で「硬い食べ物だけを食べればいい」というわけではないことをお伝えしました。
実際は、食物繊維が多い食べ物、弾力のある食べ物などをバランスよく食べることが重要で、おすすめの食品等については「子どもの顎を鍛える食べ物・おやつ|きれいな歯並びに導こう」をご覧いただければと思います。
今回は、子どもが食べ物を噛めない・噛み切れない原因や歯科医院での対策方法について解説します。お子さんの噛む力を健やかに育てたい保護者の方はぜひ参考にしてください。
目次
■子どもが食べ物を噛めない・噛み切れない原因
◎噛み合わせの異常
子どもが「噛めない」「前歯で噛み切れない」と訴える場合、噛み合わせの異常が原因となっていることがあります。
たとえば、前歯の噛み合わせが深すぎる「過蓋咬合(かがいこうごう)」や、上下の前歯が逆になっている「反対咬合」などは、食べ物をうまく噛み切ることができない場合があります。
噛み合わせの異常は見た目の歯並びだけでは判断できず、顎の成長や筋肉の発達に影響を与えるため、注意が必要です。
◎舌や口周りの筋力不足
最近では、舌や唇、頬の筋力不足によって噛む力が十分に発揮できない子どもも増えています。舌を上手に使えないと食べ物を奥歯に送り込めず、噛み砕く動作をスムーズに行えません。
また、口をポカンと開けている習慣があると、口輪筋が弱まり、噛む動作自体が非効率になってしまいます。こうした筋力不足は、単に硬い食べ物を与えるだけでは改善されないケースもあります。
◎姿勢や生活習慣の影響
噛めない原因はお口だけに限りません。猫背や椅子に浅く座るなど、悪い姿勢で食事をすると顎に力が入りにくくなります。また、柔らかい食事ばかりを与える、長時間のスマホやゲームで口周りの筋肉を使わないなどの生活習慣も、噛む力を弱める一因となります。
■子どもが噛めないのは口腔機能発達不全症?
子どもが「噛めない」「前歯で噛み切れない」と感じる場合、その背景には口腔機能発達不全症という病気が関わっていることがあります。これは、厚生労働省でも注目されている新しい概念で、噛む・飲み込む・話すなどの機能が年齢に応じて十分に発達していない状態を指します。
口腔機能発達不全症は、歯並びや噛み合わせの乱れ、舌の位置異常、口呼吸などと関連が深く、そのまま放置すると将来的にブラケット矯正などの治療が必要になるリスクも高まります。
さらに、しっかり噛めないことは消化器系への負担や、集中力・学習面にも影響する可能性があるため、注意が必要です。
当院にも「子どもが食べ物をよく噛まずに飲み込んでしまう」「顎が小さいように感じる」といった相談で来院される患者さんも。こうした場合は歯科的な診査を行い、必要に応じて専門的なトレーニングや治療を提案しています。
■子どもの噛む力を育てる方法は?
◎MFT(口腔筋機能療法)
当院では、噛む力を根本から育てる方法としてMFT(口腔筋機能療法)を導入しています。これは舌や唇、頬の筋肉を正しく使えるようにするトレーニングで、噛む力だけでなく発音や飲み込みの改善にも効果的です。
たとえば「舌を上顎につける」「唇をしっかり閉じる」といった基本動作を習得することで、自然と正しい噛み方が身につきます。
◎姿勢の改善
正しい姿勢は噛む力を発揮するための基本となります。背筋を伸ばして椅子に深く座り、両足をぴったり床につける姿勢を心がけることで、顎にしっかり力が伝わります。
浅井歯科医院では、食事中の姿勢や椅子・机の高さについても保護者の方にアドバイスを行っています。
◎食育指導
食事の工夫も重要です。単に硬いものではなく、噛み応えのある繊維質の野菜や弾力のある肉類、よく噛まないと飲み込めない食品を取り入れることで、自然に咀嚼回数が増えます。
例えば、れんこんやごぼう、イカやこんにゃくなどは噛むトレーニングに適した食材です。当院では保護者の方に食育の視点からアドバイスを行い、日常生活での実践をサポートしています。
◎定期的な歯科受診
噛み合わせや歯並びに問題がある場合、定期的に歯医者を受診することで、早期に異常を発見することができます。その結果、歯科医師から良いタイミングで成長期を活かした治療やトレーニングを受けることができ、将来的に本格的な矯正を避けられるケースもあります。
当院では、必要に応じて矯正治療のご案内も行い、子どもの健やかな成長を長期的に支えています。
■まとめ
「硬い食べ物を食べれば顎が鍛えられる」という考えは必ずしも正しくありません。子どもが噛めない原因には、噛み合わせの異常や舌・口周りの筋力不足、姿勢や生活習慣など複合的な要因が関わります。
浅井歯科医院ではMFT、姿勢改善、食育指導を通じて口腔機能発達不全症への対策を行っています。お子さんの噛む力に不安を感じる保護者の方は、早めの歯科相談をおすすめします。